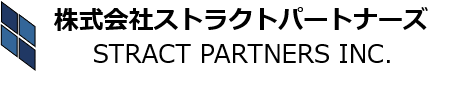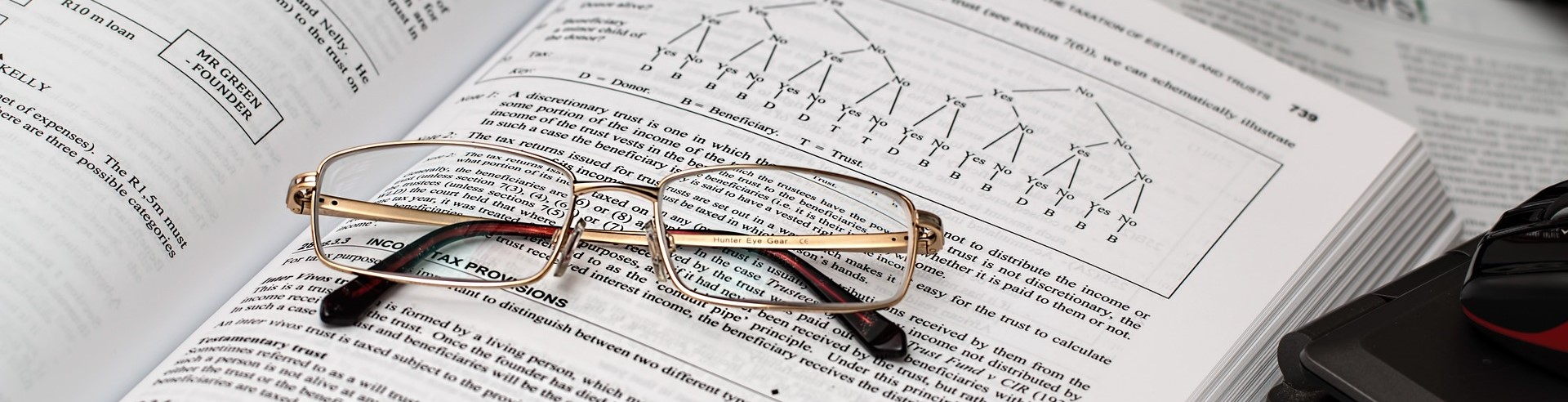会社設立時、決算期をいつにしようか? と悩まれる方は多いと思います。
通常は、短期間での決算申告の回避や消費税の免税期間(インボイスが始まるのでこの点は薄まりますが)の兼ね合いもあり、「4月設立なら3月決算」というように設立から事業期間を丸々1年とれるようにすることが多いと思います。
果たして、それだけで決めてしまってもよいものでしょうか?本コラムでは3つの観点から決算期をいつにするべきかを考えていきたいと思います。
1.設備投資の観点
季節変動などで月ごとに業績の変動が大きい場合、会計期間の前半に売上の大きな月(または利益の大きな月)を持ってくることで、計画との乖離が大きくても決算までに時間的猶予があるため、投資に回せる利益の見通しがつけやすくなるなど、計画的に設備投資や節税などを行うことができ、利益予測が立てやすくなります。
2.銀行融資の観点
銀行などの金融機関は、3月が決算、9月が中間決算というのが基本です。この3月と9月は、金融機関も目標達成のための追い込み期間となります。試算表でも対応は可能ですが、より信頼性の高い最新の決算書をこの期間に提出できることが望ましいと言えます。
決算書が出来上がる時期は、決算期→申告期間(2ヶ月)→決算書提出というのが一般的な流れですので、3月か9月に申し込むには、決算期は12月、6月あたりが理想的と言えます。
※12月決算は確定申告時期と重なるので顧問税理士が難色を示すかもしれませんが。。
3.税務調査の観点
税務署は7月から始まり6月までが事務年度となります。税務調査の頻度は9~11月が多く、12月~3月は年末調整と確定申告のため減少、4月~5月にも増加となります。事務年度前半の調査(9月~11月)の方が長期で臨むことができ、事務年度後半の調査(4月~5月)は年度の終わりが近いので、長期化が見込まれるものは着手しにくいと言われています。
また、税務調査中に会計期間が終わってしまうと、処理を決算に織り込む、織り込まないといった問題が発生します。そのため、3月~8月決算の会社が9月~11月に、9月~2月決算の会社が4月~5月に税務調査着手となることが多いようです。
このように税務調査の観点からは決算期は9月~2月が良いということになります。
この銀行融資と税務調査の観点で考えると11月または12月が理想的ということになります。
以上、これらの観点を考慮したうえで、自社に合った決算期を決めることをお勧めします。